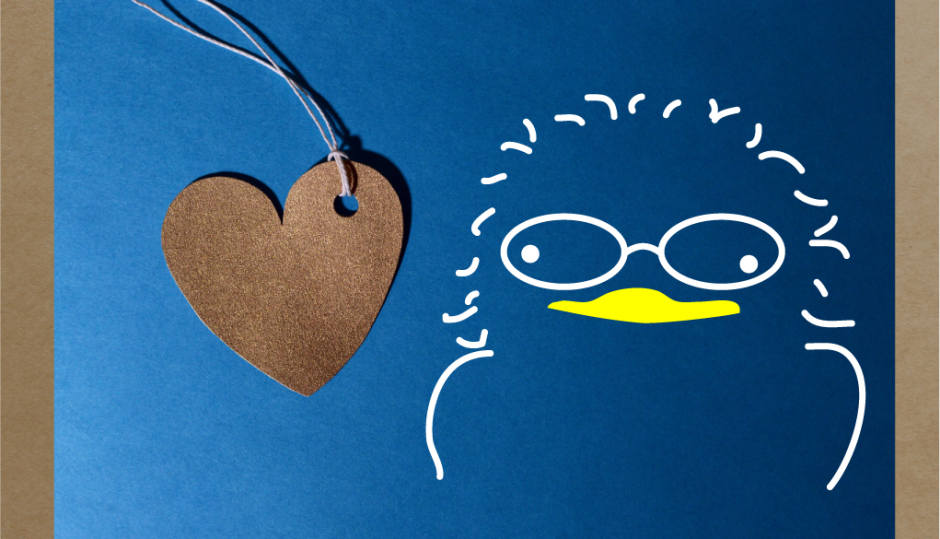中学校の想いではあまり良いものではありません。多感な時期、ということもあるのでしょうが、自分がいかに狭い世界で生きてきたかが分かった時期だからです。私は、祖父が教育長、叔父が高校教諭、叔母が中学教諭と幼稚園教諭、そのほかも県庁職員だの研究者だのって、偏った職業の家庭(父と母は全く関係ないですが)で育ったので、無条件に「先生」を信じる傾向にありました。教育者は人格的にも素晴らしい存在だと。実際、小学校までの先生方は、私の目にはそう映っていました。でも、中学生になるとそういう先生たちも「人間」なんだということが見えてくるのです。エゴや贔屓は当然、自己顕示欲や階級差。そんなほの暗いものが見える先生がいらっしゃいましたが、そういう方からみると、私はとてつもなく嫌な存在だったらしく、いわゆる「教師からのいじめ」を徹底的に受けました。それでも私はまだ「教師」を信じていて。中3の受験までいろいろありましたが、最後の最後、卒業の手前でその方とは違う先生から、半ばあきれ、半ば感心した様子で「あれだけのことがあってもあなたはまだそうやって普通に話そうとするんだね」と言われたくらいです。その言葉、その時は意味が分かりませんでしたが、今思うと先生方にしたら恐怖だったのかもしれませんね。だって何しても何しても笑顔で寄ってくるんだもの。ゾンビ扱いだったかもしれません。
別にその先生が好きだったわけではないのです。当たり前ですが、嫌い、というか理解不能な存在でした。どうして自分だけ怒られるのか、どうして自分だけ仲間外れにされるのか(私は掃除を命じられていて体育教官室の掃除をしていたのですが、その間にクラスで卒業のお祝い(先生がジュースをおごってくれていた)の乾杯とかをされたり。全員そろったなとか言って。意味わかんないよね)全然わからなかった。でも、先生が怒るのはきっと自分が何か悪いからだとずっと考えていて、どうやったら先生に認めてもらえるかと思っていました。無駄なんですけどね。だって先生は私のことが嫌いだから。そこは判らないのです。「教師」は「生徒」を平等に扱うものだと信じているから。自分でもわからないですが、おそらく今同じことがあっても、やっぱり私はその先生を憎むことはないと思います。
嫌なことは「現象」としては覚えていますが、(それも半端なく細かいところあまで)それが個人への憎悪にはつながらない。そういう性格なのでしょう。
嫌いな人は嫌いですが、憎むことはないのです。それを「優しい」と取るのか「執着がない」と取るのかはわかりません。執着するって結局その人に興味があるということ。私は多分執着を手放すことで、自分の心を守っていたのかな、そういうテクニックをすでにこの時期覚えていたのかなと思います。
人が大好きですが、人は怖い。「人間」というものを学問的に知りたいと思ったのは中学生の時期がきっかけです。
教師と同じように両親のこともずっと「信じて」いました。今思うと(というか今も)精神的虐待に近いことがありましたが、それでも親は親。やっぱり憎めないのです。
幼稚園の時、母に言われた言葉が私を今でも縛ります。鎌倉大附属に行きたくないといったときのことです。
「良い小学校に入ると、良い中学校に行けて、良い中学校だと良い高校に行ける。良い高校から良い大学に入って、大学院に行ってもいいわね。そうすると良いところに就職できるから素晴らしい人と結婚できる。素敵なお嫁さんになって、子どもは2人。毎日が幸せよ」
言葉による呪縛。「良い」の意味が分からない。今でもわかりません。
だって、良いといわれて入った中学は、私にとって良いところではなかったから。でも、この言葉がその後の私の人生の基軸であったことは事実です。いつだって照らし合わせる。私は母の言うとおりに生きてきているか?いうことを聞かなかった今の自分は評価されなくて当然なのではないか?
答えはそうじゃないことは知っています。でも、頭でわかっていても心がそれを許さない。親子関係とは本当に重要で、そして大切なものだと思います。
あまり楽しい話ではありませんが、親との関係が自分の人生にとってとても重たいものなので、やっぱり少しずつ書かざるを得ない感じだな・・
リコの書くブログ012