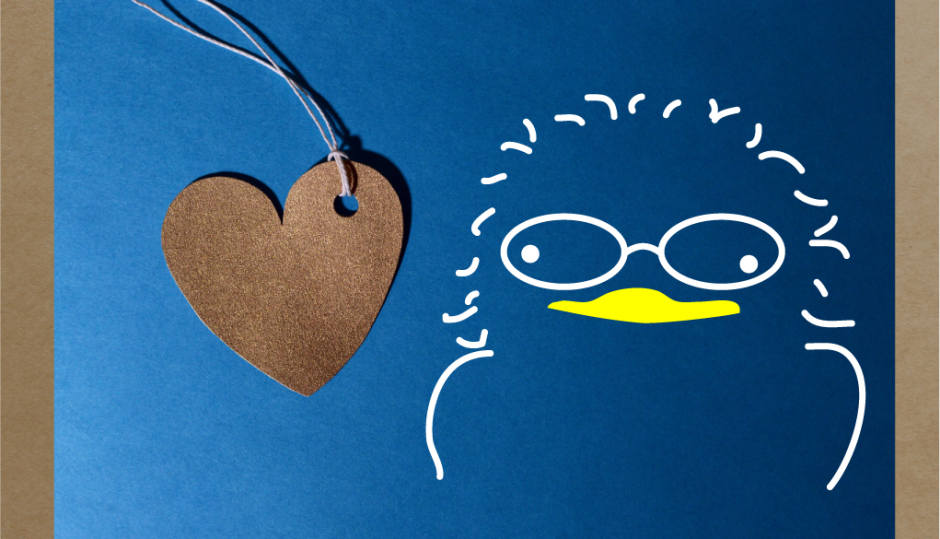「私、英語ではなくどうしても生物ができる学校に行きたいんです」
「DNAの二重らせんがきれいで!!!」
先生の前に座った私が切り出したのはこのセリフ。
絶対、私立外国語類型の生徒の口からでる内容ではゴザイマセン。
でも、先生はニヤっと笑って「あなたの人生なんだからいいんじゃない?」と。
まるで私がこういってくるのを判っていたかのように取り出した資料が
「早稲田大学人間科学部」。当時まだ3年目の新設学部でした。
「ここはね、受験科目が英国小論、文系科目受験であなたがやりたい生物ができるんだよ。ほかに心理学と社会学もできる」
「小論は僕が指導してあげるから」
・・・ってさあ、もうこの進路しか見えなかったですよ。だって、社会学は無茶苦茶興味あったし、人間に関わる心理学も当然好き。さらに生物学でしょ??
しかも先生の指導付き!!! なんか今まで生きてきてよかったとか、そういうテンションでした。
この時期が3年の11月かどうかなんて、まったく気にならなかったし、早稲田大学の偏差値とか、一切関係なく、「私ここに行く!」と即決しました。というか、先生の小論指導のことしか考えてなかった。うん。若いってすごいわ。
と、大変舞い上がっていたわけですが、進路を変えるって結構大変なことでした。講師室を出たその足で担任に相談(決して親ではないあたりが笑える)。
3年間受け持ってくれた、英語の優しい先生は、興奮気味な私の話をだまーって聞いた後、初めて聞く位深いため息をついて一言。
「だって吉田さん、ダメって言っても受けるんでしょ?」
「はい、そうです」
「じゃあ、もう僕は何も言わないし、だけど確実に受かる大学も選んでね」
「はい、わかりました(#^^#)(全然わかってない)」
進路変更、5分で終了。本当にありがたい先生方、ありがたい学校だと思いました。ちゃんとやりたいことを応援してくれるの。まあ、ダメ元だとも思われたのかもしれませんけどね。でも、そんなこと全くわからないように接してくれました。
大変なのはこの後。両親の説得です。
父が私に求めたのは「女子大で、英語」東京女子大とか、津田塾とか、日本女子大を狙えと言われていました。でも私は大学は共学が良くて、女子大にはいきたくなかったのです。
母が私に求めたのは「英語」のみ。彼女の中で私は将来「英語を武器に世界をまたにかける仕事(国連がよかったらしい)をして、将来日本をしょって立つ人と結婚して、専業主婦(ここが意味不明)」になる予定だったらしく、だけど世間を知らないので「英語」ができればそれがかなうと思っていたらしいです。
そもそも、国連で世界をまたにかける仕事したら、専業主婦なんかならないよ。私はそういう人間ですから。でも、母の中の「仕事」はあくまで一般職。そんな人は世界をまたにはかけません、という矛盾には気が付かないのです。
時代とは言え、社会というもの、女性の生き方ということにとんと理解がないというのはこれほどまでに視野を狭めるのかと、今となっては恐ろしく思います。私は起業以来、ジェンダーの問題、働き方改革ということをずっと念頭に置いてきました。女性であることで社会的に制約を受ける世の中はやっぱりおかしい。
自分で選択して、自分で責任をとる生き方をしたいと、このころから感じていたわけです。
さて、最大の問題は二人とも私が教師になることを認めていなかったこと。母は教師という職業が大嫌い(大変くだらない理由で)でしたから、幼稚園の時から先生になりたい私とはまったく話が合いません。私が最初から教育学部を選べなかった理由はここでした。最終的に「教員なんて大嫌いだから、お前が教員免許を取るのならば親子の縁を切る」と言われて、教員になることはあきらめざるを得ませんでした。だから志望校が決まらなかったというのもあります。今ならば、縁くらい切られてもどうってことありません(というか切りたい)が、18歳の私には親子の縁を切られてしまったら生きていけないと、絶望していました。
そういう親に「生物をやりたいから志望校を変える」ということは、大変勇気がいります。恐る恐る切り出してみましたが、1週間は馬鹿にして口もきいてくれませんでした。私が生物の先生を好きなことも知っていたので、先生にたぶらかされている、娘の人生を台無しにしやがって、文句を言ってやるとこれまた大変。先生は「君の人生だから」と言ってくれたのに・・それだけは止めなければと、私も必死でした。
とにかく何度も話しかけた結果、父は「浪人しない」「女子大を受ける」ということを条件に許してくれて。母は「教員免許がとれない(当時はスポーツ科学科だけが保健体育の免許がとれたけれど、他は無し)」という理由と「早稲田大学」というブランドで納得してくれました。二人とも最初から受かるなんて思ってなかったみたいです。